クイーン『シアー・ハート・アタック』70年代ロックの傑作には、「このアルバムにシンセサイザーは使っておりません」とクレジットされていた [世界のロック記憶遺産100]

たますびの町山智浩さんのクィーンというかフレディ・マーキュリーの映画『ボヘミアン・ラプソディ』の解説がむちゃくちゃでびっくりしました。
クイーンが出てきた時っていうのは『Killer Queen』っていうレコードで出てきたんですけども。リードボーカルの人がはっきり言ってすっげーブサイクなんでみんなびっくりしたんですよ。
「ええっ、ちょっとお笑いに近くねぇ、これ!」という感じだったんです。はっきり言って出っ歯だし。それはこの『ボヘミアン・ラプソディ』っていう映画の中でもすごく最初の方で描かれるんですよね。フレディ・マーキュリーさんっていうボーカルの人にとっては、顔が独特であるということは映画の中でも大きな大きなテーマになっているんですよ
映画ではそうかもしれないですけど、僕らの子供の頃はフレディって貴公子で、ドラマーのロジャー・テイラーと人気を2分する大スターでした。当時のロック美少女(現在おばあちゃんですよね。失礼!、すいません)に確認すると「フレディーも大人気でしたよ!日本の女の子の方が彼のエキゾチックな魅力に抵抗がなかったはずで黒髪と切れ長の目に夢中になっていました!そこが日本のファンの誇れるところでもあります」とのことです。町山さんを擁護すると「音楽雑誌の読者投稿でいじられてたのを人気ないと思っちゃってたのかなー。美少年=金髪碧眼の幻想を越えるのに多少時間がかかったかもしれないですけどね。」とのことです。
ドラマーが一番人気があるって、どうかと思いいますが。渋谷陽一さんは「この顔がこれからのロックの顔だ」要するにロバート・プラントンやフレディ・マーキューリーのような長髪で男性フェロモンむき出しの顔でなく、ロジャー・テイラーのようなシャープな顔立ちがロックとなるだろうと予想したわけです。その予想はパンクの登場により見事的中するのですが、今思うとロジャー・テイラーの顔って歯医者さんの顔だったんですよね。ホンマに元歯医者だし。渋谷崇拝者の僕はロジャー・テイラーがこれからのロックだとずっと思ってたわけで、思わず映画『ハング・オーバー!』のギャグ「歯医者は医者じゃねぇ」と叫びたくなります。
そんな中(どんな中だ)ギターのブライアン・メイとベースのジョン・ディーコンは無視されるみたいな、これはいい過ぎですけど。僕はブライアン・メイのギターが大好きだったので、当時の日本のファンの扱いには不満でした。だから女はバカなんだと思ってました。ウソです、10歳の子供なんでそんなそんなこと思ってませんでした。コンサートやフィルム・コンサートに行けば、ビオランを着て、クルクルパーマを当てたお姉さんが、ジェラルミンのケースから飴、ガムをくれたり、アーティストと一緒に撮った写真を見せたりしてくれました。ジーン・シモンズのあそこのポラロイド写真とか「僕にはまだ早すぎるかな」といいながらチラっと見せてくれました。
映画「あの頃ペニー・レインと」の主人公キャメロン・クロウはまさに僕そのままなんです。でも僕はキャメロン・クロウみたいにアーティストにはインタビュー出来ず、小学生の友達に「外人はチンポがデカイ、しかもあそこの毛は金髪だぞ」と触れ回って、漫画『トイレット博士』のメタクソ団に対抗して、金髪団を結成しました。何をしてたかというと、日夜銭湯に行き、外人が入って来たら、そいつのチンポの毛を確認するという研究を始めたのです。すいません、昭和の子供で。
ビオランって今ネットで調べても出て来ないですね。フリートウッド・マックのスティーヴィー・ニックスが着ているような服、いやちょっと違うな今でいうとゴスロリのファッションに近い、きっとその源流なんでしょう。日本はいつだって一緒です。そんな格好をしたお姉ちゃんたちがなぜか小さなペラペラの鉄かなんかで出来たジュラルミン(だからジュラルミンじゃない)のケースを持っていたんです。男も持ってたんですけど。当時5千円くらいだったと思います。10年くらい前まではまだ大中とかで売っていたと思います。僕も欲しくって、欲しくって仕方がなかったんですけど、なかなか買えなくって、買える頃には僕はパンクになっていたので、子供の頃の夢だったからなんか知らんけど買ってしまったが、もう持ち歩くには恥ずかしく、家の小物入れに使うくらいしか用途がなかったです。
こんな僕のバカな話よりまずブライン・メイのギターを聴いて欲しいです。世界のロック記憶遺産100ヴァン・ヘイレン『炎の導火線』で、エディ・ヴァン・ヘイレンのギターが現在のロック・ギターの原型であると書きましたが、その一番のルーツとなるギターがブライアン・メイなのです。まさに革新だったのです。いろんなエフェクターがかけられ(と言っても今と比べると対したことないですよ)、フランジャー(まだなかったと思いますが、どうやってやってたんでしょう)、ディレイ(アンプを3台使って、距離的にも本当に遅れを出していた。広がりがあるだけですけどね)、シンセだと当たり前なデチューンや5度や7度の音をブレンドさせること、(どうやってやってたんでしょう。2回弾いていたのか、)とにかくブライアン・メイのギターの音色は過ごすぎて、“このアルバムにシンセサイザーは使っておりません”とクレジットされるくらいだったのです。

(残り 2370文字/全文: 4578文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。
タグマ!アカウントでログイン
tags: Eric Clapton Queen Van Halen 宇都宮カズ 東郷かおる子 町山智浩







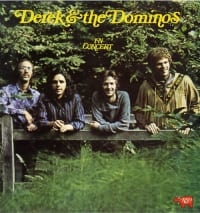


外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ