オレじゃない誰かとつきあった方がいい—生きているのか死んでいるのかもわからないNのこと[3]-(松沢呉一)
「母親との共依存からの脱出—生きているのか死んでいるのかもわからないNのこと[2]」の続きです。
彼女は一人で決断して実行した
![]()
Nが一人暮らしを始めたのは、出会ってから1年足らずのことだったのではなかろうか。
「松沢さんの言った通りにしたよ。褒めて」と請うような口ぶりでもあったので、私は「よくやった」と讃えました。あれだけ一人暮らしをすることに抵抗していたのに、あまりにあっさりと実現したことに驚きつつ、一人で決断して行動したことを私自身、好ましく思いました。母親と距離を置いた方がいいことは彼女自身よくわかっていて、わかっていながらも実行ができない。そんな時に私が登場して、いくらかの葛藤がありつつも、私の言葉を自分の力にしたようでした、
「遊びに来てよ」
私は彼女の新居に行きました。学芸大駅のすぐ近くです。いくらか忘れましたが、駅から近いわりには安かったのは、すぐ近くを東横線が走っていて、線路音がうるさかったためです。
電車の音は庶民的とも言えましたが、部屋の中は「生活感がない」というのが第一印象です。
 必要のないものは実家に置いてきたため、とにかく物が少ない。冷蔵庫とベッドと背の低いガラスのテーブルくらいしかない。本箱もない。ワンルームだったのですが、それでも広々としていて、十分な広さでした。
必要のないものは実家に置いてきたため、とにかく物が少ない。冷蔵庫とベッドと背の低いガラスのテーブルくらいしかない。本箱もない。ワンルームだったのですが、それでも広々としていて、十分な広さでした。
何度行っても部屋には家具は増えていかず、殺風景さは変わりませんでした。
彼女は本や漫画が好きなのですが、読むと捨てます。溜まったら束ねて再生ゴミとして捨てるのではなく、ゴミ箱の中に捨てる。ゴミ箱の中の本を見て、「もったいないことするなよ」と言ったこともありました。
「だったら、持って行っていいよ」
実際に何冊かもらったこともあります。よく覚えているのはモデルの中川比佐子のダイエット本です。中川比佐子は1980年代を代表するような存在であり、モデルの域を超えたオピニオンリーダーでもありました。その本には彼女が太った時の写真が掲載されていて、軽く面識のあった私には衝撃でした。すっぴんの写真で、道で会ってもわからない自信があります。
Nは華奢な体つきで、食も細い。ダイエットしたかったのではなくて、私と同じく衝撃的な写真で買ったのでした。
本に限らず、彼女は物を捨てる能力に長けてました。物を残さないで捨てる。食べ物や飲み物もそうです。彼女はたまに「ちょうだい」と言って私のタバコを吸うことがありましたが、ふだんは吸わない。私が吸うと、吸い殻をすぐさま灰皿からゴミ箱に捨てます。テーブルに落ちた灰もティッシュで拭います。
呪縛が解けた
![]() それまでは一緒にいても数時間だったのが、ここからは彼女の家に行き、朝まで一緒にいることが増えます。相変わらず、月に1回とかそんなものだったと思いますが。
それまでは一緒にいても数時間だったのが、ここからは彼女の家に行き、朝まで一緒にいることが増えます。相変わらず、月に1回とかそんなものだったと思いますが。
前回書いたような、いわば「セックス思想」から、私はどちらかの家でセックスをすることを避けていて、1回か2回家に行くことはあっても、あとはラブホになる。ラブホであれば休憩で2時間か3時間。泊まりでも朝まで。長い時間設定のラブホでも昼まで。終わりの時間が設定されているので、けじめがつきやすい。
その点、Nとの関係は異例でした。これは私が「一人暮らししろ」と言ったことの責任のようなものです。また、私が朝帰る時にベタベタとしてきて「もっといてよ」なんて言うこともない。そういうあっさりとしたNの性格が彼女の家に泊まることの抵抗をなくしてくれました。
物が少なくて整頓されていることと、もうひとつ彼女の部屋には特徴がありました。暗いのです、彼女は天井の蛍光灯を使わず、壁に当てた間接照明だけを使います。 私が行く時だじゃなく、いつもそうです。
 彼女は近眼で、外ではほとんどつねにコンタクトをしていて、家では眼鏡も使ってました。本を読む時も天井の蛍光灯は使わず、卓上のライトを使う。
彼女は近眼で、外ではほとんどつねにコンタクトをしていて、家では眼鏡も使ってました。本を読む時も天井の蛍光灯は使わず、卓上のライトを使う。
その方がたしから粗は見えない。壁のシミは見えないし、すっぴんでも私の前に出られる。
食べ物屋であればその方が落ち着くのでしょうが、生活の場としては暗いと落ち着かないってことを私は知りました。
たぶんあれは物で自分らしさを作り出すのではなく、照明で自分らしさを作り出していたのだろうと思います、彼女の趣味ですから、それについては何か言ったことはありません。
母親の呪縛から逃れたことによって、彼女は伸び伸びしているようにも見えて、白目の癖がこの頃から消えていき、気づいた時にはきれいにやらなくなってました。なぜ白目になるのかまったくわからないでいたのですが、消えて初めて、精神的軋みから来ていたものだとわかりました。
鼻の奥を鳴らす癖は白目に比べると奇異にとらえるほどではなく、「ちょっとした癖」という程度に受け取っていたため、そうは意識していなかったのですが、たぶんこちらもいつの間にか消えていたと思います。
モデルの仕事は続けていましたが、それでは食えないので、Nは水商売を始めました。母親と同居していた頃だったら許されなかったでしょう。彼女はこのあとも何軒かで働いていたので、いつどんな店で働いていたのかは覚えていないですが、フェティッシュバーの類で働いていたこともあったはずです。
そういう店は接待で使われることも多くて、「集英社の客がこんな話をしていたよ」と情報を流してくれることもありました。

(残り 3250文字/全文: 5470文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。







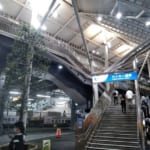
外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ