韓国系米人編集者マット・キムのこっ恥ずかしい「アサクリ シャドウズ」擁護論—文化盗用とパクリ[17]-(松沢呉一)
「「アサシン クリード シャドウズ」が歴史に残る大炎上—文化盗用とパクリ[16]」の続きです。
IGNの韓国系米人編集者による「アサクリ シャドウズ」擁護論
![]()
ここまで書いてきたことだけなら、あちこちで議論が続いているので私の出番はなく、この話はスルーしたかもしれません。
しかし、以下を読んで呆れ返って黙っていられなくなりました。
2024年5月18日付「IGN」
この文章は、「アサシン クリード シャドウズ」を擁護したものとして、ボロクソに叩かれているので、その上に重ねて批判する必要はないのですが、ここまで書いてきたように、「日本の文化」「日本の伝統」「日本の歴史」を「アジアの文化」「アジアの伝統」「アジアの歴史」のように記述することで、自分もその当事者であるかのように見せかける偽装がなされていますので、触れないわけにはいかない。
この一文をざっとまとめると、「侍を主人公にしたゲームは多数ある。もう飽きたので、黒人の侍がいてもいいじゃないか」てなところです。
私自身、「また侍か」との思いはあります。しかし、近代の戦争になると敵国が登場するため、触れにくくなり、日本を舞台にしたバトルは戦国時代か幕末にならざるを得ない。それでも、そこに飽きが来ていない人が多いから、侍を取り上げる映画、ドラマ、ゲームが送り出され続けているわけで、その現実より、「飽きた私」を上位に置いて、他国の歴史を捏造することを肯定。あんた、何様?
この議論において、自己が肥大した筆者が「飽きたか、飽きてないか」「黒人を出せば飽きがなくなるか」なんてことはどうでもいい。そんなに熱心に情報を追っているわけではない私でも把握できている論点を完全に無視しています。理解できていない、あるいは理解できているのに、バカのふりをしています。
この筆者であるマット・キム氏は、ゲーム・メディアIGNの編集者です。日本のゲーム・メディアもしばしばそうであるように、スポンサーであり、情報の最重要な情報源であるゲーム業界に媚びる記事を出さざるを得なかったのでしょう。知らんけど。
その目的が決定している中、正面から議論に挑むことはできず、せいぜい論点ずらしをするしかない。結果、UBIソフトに対する批判を分散する効果くらいはあったかもしれず、UBIソフトに物乞いする資格はゲットできたでしょう。よかったですね。
都合よく出自を持ち出して歴史改竄を肯定する
![]()
マット・キム氏は文中で「アジア系アメリカ人としての私」と「韓国系アメリカ人である私」を都合よく使い分けています。第三者が個人の出自に言及するのは行儀のいいことではないですが、「アジア人」と「韓国人」という属性の「私」のみを論拠にした文章であり、それを外したら意味を失くす一文を正しく評するにはそこを見るしかない。
「アジア系アメリカ人としての私」であるマット・キム氏は「アジアのサムライ」と表現しています。侍は「Samurais」としていますから、地域を問わず、広く一般に「刀を持った戦士」を指しているのでなく、日本の侍です。
 欧米の視点で、非欧米をどう見せたかったのかという大きな枠組みにおいて、「欧米とアジア」という対比になるのは理解できます。
欧米の視点で、非欧米をどう見せたかったのかという大きな枠組みにおいて、「欧米とアジア」という対比になるのは理解できます。
また、日本から見て、遠いエリアはざっくりとした表現をします。「クスクスはアフリカの主食」と言ったり。実際には北アフリカです。あるいは「チャルガは東ヨーロッパのポップス」と言ったり。チャルガと同種の音楽はバルカン諸国に存在してますが、各国呼び名が違い、チャルガはブルガリアです。
「細かいことを言ってもわからんよ」という場合はエリアは曖昧になる。しかし、日本人に馴染みのあるエリアでは、何かそうすべき事情がない限り、所属がはっきりしている文化を取り上げて、「北京ダックはアジアの食べ物」とは言わない。「K-POPはアジアの音楽」とも言わない。その国の文化を尊重する気があればそんなアバウトなことは言わない。
といった法則がありますが、この文章で「アジアのサムライ」と書かなければならない事情がわかりません。自分が当事者であるかのように見せるためだろうと思うしかない。
その上で、「侍はもう飽きた」「多様性がない」と言っています。そのために黒人の侍がいてもいいじゃないかと。「多様性侍」を出すためなら、歴史を改竄、捏造していいわけです。さすが改竄、捏造を得意とする民族です(なんて当てつけのひとつも書きたくなります)。
この手法は、中国系団体「Stand Against Yellow Face」が日本の着物を「アジアの伝統文化だ」として、着物の理解を促進するイベントを妨害したことにも見られます。他文化を否定するための小賢しい詐術です。
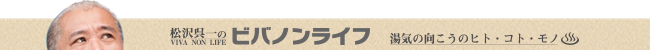
(残り 1164文字/全文: 3153文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。

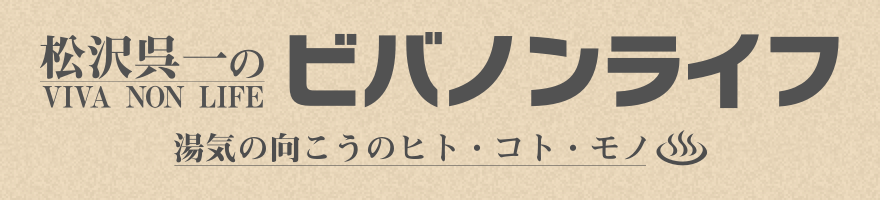







外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ