明菜復活! 元マネージャーが語る、時代を駆け抜けたアイドル・中森明菜の素顔
■中森明菜、7年ぶりのステージへ
沖縄に通っているのは「高江」の状況を取材するためだけではない。
いま、どうしても会っておきたい人物がいた。
中森明菜の元マネージャーである。
那覇市内で彼と久々に顔を合わせた。
「いよいよ始まりますね」
そんな私の言葉に、彼は複雑な表情を浮かべながら「うまくいくことを祈っていますよ」と返した。
明菜が実に7年ぶりのステージに立つ。
「体調不良」を理由に明菜がコンサート活動を中断したのは2010年の秋だった。
一昨年の紅白歌合戦に米国からの中継という形でサプライズ出演を果たしたものの、その後も、ステージには立っていない。
しかしいよいよ来月から全国各地でディナーショーをおこなうことが発表された。
いずれの会場でもチケットは即日完売。現在、ネット上では定価(約4万円)の倍の価格がつけられて転売されている。
実は、私もどうにかチケットを確保した。
来月の公演がいまから楽しみで仕方ない。
私は明菜が好きだった。いや、いまでも好きだ。顔が好きで、声が好きで、不器用そうな笑顔が好きだ。両手で抱えた幸せを、地面に叩きつけて壊してしまうような理不尽さも好きだ。彼女には、80年代というスカスカの時代をともに過ごしてきたという、同世代者としての親近感もある。
アイドルとは、時代の業を背負った存在だ。歓喜と苦渋を血肉とし、歴史に鮮やかな刻印を残していく。しかしいま、アイドルという存在から発せられるのは、あざといマーケティングの槌音だけだ。
明菜という存在にも、そうした側面はあったかもしれない。だが、私のひいき目を許していただけるならば、彼女は「時代」そのものだった。自立と挑戦と破滅を、見事に演じた。
80年代とはそういう時代だったのだ。
浮かれていた。何か素晴らしいことがあるかもしれない「未来」を誰もが予見することが可能だった。ひどく目の粗いザルで世界掬い上げても、確実に手ごたえを感じることができた。
1982年──バブル一歩手前という時代の空気を吸い込んで、芸能界もまた、熱い思いと、いい加減な成り行きで盛り上がりを見せていた。
掘ちえみ、新井薫子、三田寛子、小泉今日子、石川秀美、早見優、伊藤さやか、そして中森明菜。
豊作だった。俗に「花の82年組」と呼ばれる。アイドルという”規格”から逸れることなく、それぞれが役割としての「花」を演じた。
明菜はすべてにおいて抜きんでていた。
登りつめ、そして引きずり降ろされ、もがき、また立ち上がろうとする。
3年ほど前には明菜の足跡をたどり、『週刊ポスト』(小学館)で「中森明菜とその時代~孤独の研究」と題した記事を連載した。
この連載記事を書籍化すべく、いまでも追加取材を続けている。
その過程で、沖縄でふたたび彼と会ったのだった。

(残り 3684文字/全文: 4818文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。




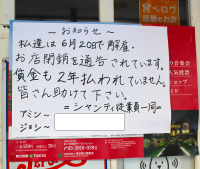


外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ