長生炭鉱事故の悲しみを歌う──ハルナユが訴えるもの
′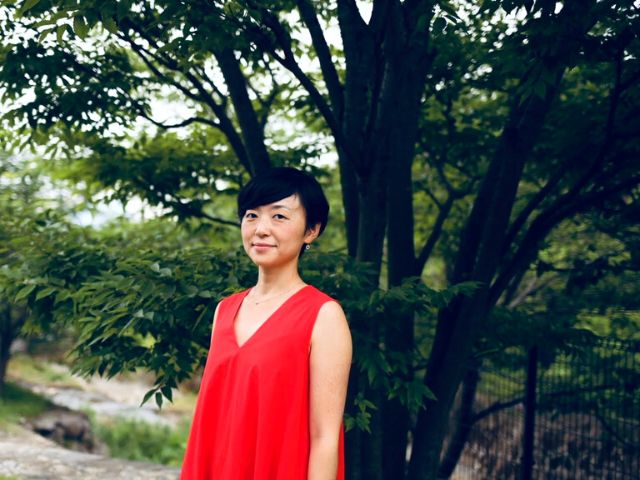
柳春菜さん(本人提供)
天神(福岡市中央区)のカフェで柳春菜(ゆうはるな)さんと会った。3年ぶりだった。
約束の時間に遅れたことを詫びる私に「問題ないですよう」と答えた柳さんの口調は、なにかの歌の一節を口ずさんでいるようにも聞こえた。いつもリズムを抱えて生きている人なんだなあと感じた。
柳さんは同地を拠点に音楽活動を続ける「ハルナユ」のボーカリストだ。
私が初めて柳さんの歌声を聞いたのは2020年1月30日。山口県宇部市の床波海岸だった。
この日、1942年に水没事故を起こした長生炭鉱の犠牲者を追悼する集会が開かれた。そこに柳さんは招かれていた。
「ハルナユ」でギターを担当する高石純二さんの演奏で柳さんが歌ったのは「カヂマヨ」(日本語で「行かないで」の意)。長生炭鉱の水没事故をテーマとした歌だ。哀調を帯びた旋律に、愛する人を失った女性の気持ちが込められていた。
行かないで 私の愛
そばにいて すぐに来て
きっとあなたは驚くでしょう
どれほどに私が熱を帯びているのか
あなたへの愛はまるで燃え上がる火の花のよう
深い深い海の底にあなたを探して飛び込んでいくの
鼓膜をすり抜けて、からだの奥深くに染み込むような歌声だった。静かに、波紋のように、周囲の風景を呑み込みながら、それは真冬の海辺に響いた。
追悼集会を終えた直後、海に向けて花を投げる柳さんの姿があった。
実は、柳さんの血縁者も、長生炭鉱の事故で命を落としている。
「なぜ朝鮮人がこの場所にいたのか。なぜ亡くなったのか。その意味を問い続けたい」
海風に当たりながら、そのとき、柳さんは私の取材にそう答えた。
長生炭鉱水没事故──この大惨事については以前にも記事にしたが(参照)、あらためてその経緯に触れてみたい。
同炭鉱は、宇部炭鉱群のひとつに数えられる海底炭鉱だった。開坑は1914年。宇部の床波海岸から周防灘沖に向けて坑道が掘られ、最盛期には年間15万トンの石炭を産出していた。
水没事故が発生したのは日米開戦から2か月後、1942年2月3日のことだった。沖合約1キロの坑道で天盤が崩壊し、海水が流れ込んだ。逃げ場はない。炭鉱労働者は瞬時にして真冬の冷たい海に飲み込まれた。
死者183名。海底での事故である。遺体はいまなお沈んだままだ。
犠牲となった労働者の多くは朝鮮人だった。その数、136名にものぼる。犠牲者全体の7割を占める。この数値こそが、当時の国策産業の実相を示していよう。
『宇部市史』に次のような記述があった。
長生炭鉱は特に坑道が浅く、危険な海底炭鉱として知られ、日本人坑夫から恐れられたため朝鮮人坑夫が投入されることになった模様であり、その当時「朝鮮炭鉱」と蔑称された
戦時増産体制のもと、安全よりも生産拡大が優先された。過去に何度か坑内出水が確認され、事故が予見できたにもかかわらず、炭鉱側は何の対策もとっていなかった。
危険作業の主力は朝鮮半島から連れてこられた労働者だ。だからこその「朝鮮炭鉱」。過酷な労働ゆえに逃亡も相次いだ。水没事故より3年前に発行された特高警察の内部資料『特高月報』(1939年11月・12月号)には、同年10月に長生炭鉱で17名の朝鮮人労働者が逃亡するも会社の労務係に捕まり事務所で殴打された、との報告がある。
日本の植民地主義と朝鮮人蔑視は、職場離脱を暴力で封じた。過酷で危険な労働現場に押しやった。そして、命を奪った。

(残り 2618文字/全文: 4069文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。








外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ