沖縄でピンクを探す-桃色探訪 第三部 後編-[ビバノン循環湯 71] (松沢呉一) -3,548文字-
「ピンク物件巡り-桃色探訪 第三部 前編」の続きです。
沖縄にはなぜピンク物件が多いのか
![]()
 その点でピンクもまた海には適切な色であり、江の電に乗っていて、鮮やかなピンクの民家を発見して、途中下車したこともある(前回の最後に出ていた写真の家がそれだったはず)。
その点でピンクもまた海には適切な色であり、江の電に乗っていて、鮮やかなピンクの民家を発見して、途中下車したこともある(前回の最後に出ていた写真の家がそれだったはず)。
あとでわかったのだが、偶然知人の実家がこの近所だった。知人によると、その家の人は「派手にしすぎた」と後悔しているとのことだったが、海の近くならあれもよし。
その湘南よりも、もっとピンクの建物が多い場所がある。沖縄だ。これもまた普通に街を歩いていて気づくほど多いわけではないのだが、ピンク物件探究者としては、ここに着目しないはずがない。
そのために沖縄に行ったのではないのだが、このことに気づいて那覇でピンク探訪が始まった。
 地元の人たちに聞いても、ピンク物件が多いことに気づいておらず、ましてその事情などわかるはずもないのだが、沖縄にピンク物件が多い理由は簡単にひ
地元の人たちに聞いても、ピンク物件が多いことに気づいておらず、ましてその事情などわかるはずもないのだが、沖縄にピンク物件が多い理由は簡単にひ
ねり出せる。沖縄はアメリカ占領下にあった時代が長いため、アメリカ文化の影響を色濃く受けている。ピンクがエロの色という日本の文化圏にないのではないか。
沖縄の看板は今も英語のものがよくあって、建物の色合いも本土のそれとは違う。したがって、それが理由になっていることは十分にあり得るのだが、基地周りの建物や国際通りの建物ならいざ知らず、それ以外の場所の商店やアパートにもピンクは見られ、沖縄らしい様式の古い民家でさえもピンクの壁が見られる。おそらく太平洋戦争以前から、この色味が使われていたのだろう。
波上宮の建物までピンク
![]() さらには那覇の海に臨む波上宮に薄い色合いのピンク物件があった。神社の建物にピンクは似つかわしくない。宮司に聞いたのだが、「どうしてでしょう」と言うのみ。色を決定した人でも、その意味がわからない。壁の色というのはそ
さらには那覇の海に臨む波上宮に薄い色合いのピンク物件があった。神社の建物にピンクは似つかわしくない。宮司に聞いたのだが、「どうしてでしょう」と言うのみ。色を決定した人でも、その意味がわからない。壁の色というのはそ ういうものなのだ。
ういうものなのだ。
次に私は土の色に着目した。沖縄では明度の高い茶色の瓦やそれに近い壁の色をよく見る。素焼きのシーサーを売っている店で聞いたところ、現在は台湾から輸入している土が多いが、もともとは沖縄の土の色だそうだ。しかし、この色とピンクは大きく違っていて、オレンジに近い。
では、染料か。紅型は、その名の通り、紅が強いにしても、ピンクではない。これも中国から入ってきた色のセンスだろうと思う。中国では赤い壁の建物をよく見かける。天安門広場も赤だし、一般の建物でも赤は非常に多い。ただし、日本で言う赤と中国の紅はかなり違っていて、日本人が赤茶や小豆色と認識する茶系統の色も紅になる。
この中国の壁の色と沖縄の壁の色は通じるところがある。東京で真っ赤の建物はほとんど見ない。神社や料亭の壁は朱である。九段にあるイタリア文化会館の赤が批判されたのも、日本の風景にはそぐわなかったためだろう。
沖縄には真っ赤な色の建物が時々あるし、中国で言う紅の色も多い。しかし、北京よりも沖縄の方がピンク物件が多いので、これも考えにくい。
「沖縄ピンク」の謎が遂に解決!
![]() いくら聞き込みをやってもわからず、「沖縄ピンク」を解明する端緒さえ見つからない。途方に暮れた私は国際通りでコーヒーを飲みながら道行く車を眺めていた。
いくら聞き込みをやってもわからず、「沖縄ピンク」を解明する端緒さえ見つからない。途方に暮れた私は国際通りでコーヒーを飲みながら道行く車を眺めていた。
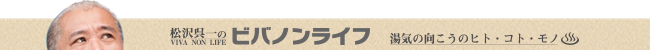
(残り 2389文字/全文: 3767文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。

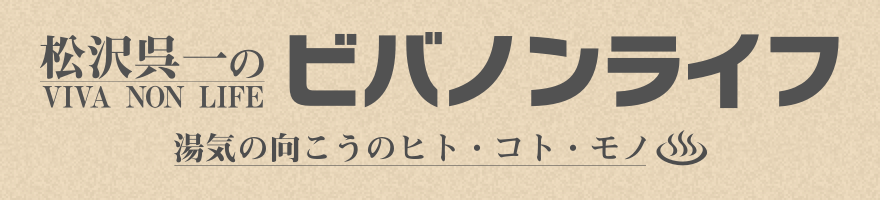





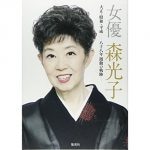
外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ