国家主義と女性の地位向上—女言葉の一世紀 137(松沢呉一)-3,522文字-
「女こそ外科医に向いている—女言葉の一世紀 136」の続きです。
こんな時代にPCを実践
![]() 前回取り上げた塩沢香著『医海きのふけふ』の著者は医事専門雑誌の記者であり、吉岡彌生は怖いという話を書いたあと、自身が体験したこんなエピソードを続けています。
前回取り上げた塩沢香著『医海きのふけふ』の著者は医事専門雑誌の記者であり、吉岡彌生は怖いという話を書いたあと、自身が体験したこんなエピソードを続けています。
斯く申す記者が駆出しの頃、女史を尋ねて先づ取材(之は記者の術語だ、世間では種拾ひと申す)の第一線、
「女医の立場から最近の御感想を……」と切出したものだ、するとその語の終らない内に、「私等は一般からも、同じ職業に従事する人々からも女医と呼ばれて居りますが、不思議な現象です。女の医師を女医と云ふのなら、男の医師は須く男医と呼ばれなければなりません」とやられ、その勢いに新米の私は多いに辟易したことがある。

「をんなこども」という言い方を俎上にあげた文章を吉岡彌生自身も書いていて、この時代にPCを実践しています。
学校名だって最初は「女医」がついていて、吉岡彌生自身、頻繁に「女医」という言葉を使用しているのですが、意味なく、つねに「女医」とされることに苛立ってていたのかと思われます。
医師は圧倒的に男であるため、ただ「医師」「医者」と呼ぶと自動的に男と思われてしまうので、誤解されると不都合が生ずる時は「女医」とするのはおかしなことではなく、著者の質問も「男の医師とは違う視点でお話ください」という趣旨としておかしくない。誰がどう見ても女であることに疑いがないのに、吉岡彌生自身、わざわざ自身の肩書きを「女医」としているものがあります(数回あとに出てきます)。
これは一発かまして出鼻をくじき、自身の立場を明確にして威圧する吉岡彌生の癖みたいなものだったのかもしれない。
と同時に、吉岡彌生は、あえて女医と区別する必要のある文脈では、「男医」という言葉も使っていますから、「両者を等しく扱う」という考え方であったことは疑いがありません。
ここまでを読むと、男女同権を主張する婦人運動家、つまりはフェミニスト的な考え方の人だったようにも思えましょうが、吉岡彌生はそれとは違います。「違う」と言い切ってしまうのもまた違う気もしますが、「新しい女」の婦人運動家とは違うのです。と言い切ってしまうのもまた違うか。
良妻賢母的教育と距離を置き、婦人運動家とも距離を起きながら、それらと完全に切断されたところにいたわけでもない吉岡彌生について知ることは、山田わかから見えてくる婦人運動の底辺とはまた違う婦人運動の暗部を知ることになります。
※1901年、東京女医学校を創立して間もない頃の吉岡彌生。Wikipediaより
吉岡彌生のもうひとつの思惑
![]() 婦人の社会的地位を向上せしめようとしたにもかかわらず、いわゆる女権論者ではない。なにがどう違うのか。
婦人の社会的地位を向上せしめようとしたにもかかわらず、いわゆる女権論者ではない。なにがどう違うのか。
塩沢香著『医海きのふけふ』で、東京女医学校の設立趣意について吉岡彌生はこう言ってます。
元来、私が女子の発育機関を設けました唯一の理由は、日支融合の契たらしめ度いと云ふ理想に基づいたものに外なりません。政府の目的が援段にあらうが、南方にあらうが、夫れは私の理想に係はりないことで、只温い情の使者として一人前の医師殊に此の使者に相応しい女の医師を一人でも多く、彼の地に送り度い希望が、遂に駆って東京女子医学専門学校の設立を為さしむるに到ったのです。
東京女医学校の設立は日清戦争(1894〜1895)が終わった五年後、日露戦争(1904〜1905)勃発の四年前。ソフトな言い方をしていますが、その時期を考えると、「彼の地に送り度い希望」は日本が大陸に、あるいは南方に侵略の歩を進めていくことの支援をしたいということだったように思えます。
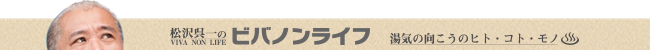
(残り 2132文字/全文: 3731文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。

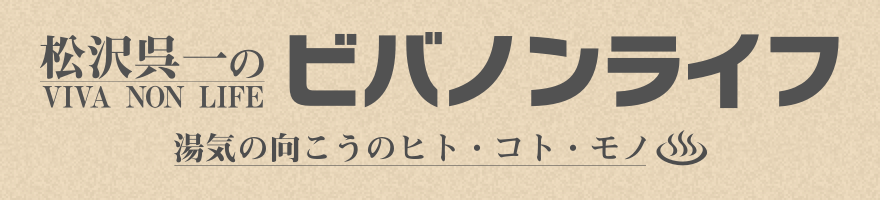






外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ