「何がポリコレだ、クソが」by 星子—「差別」を利用する人々[2]-(松沢呉一)
「「ダンダダン」は段田男から? 「肉汁餃子のダンダダン」から?—「差別」を利用する人々[1]」の続きです。
同人誌やファンアートが黙認される範囲
![]()
前回見たように、アニメ「ダンダダン」のカットを黒人にアレンジして販売している自称アーティストのLynn6Thorexという人物が大炎上。最初に絵を見た時、私は「これはいいんでないかい?」と思ってしまいました。
日本の著作権法で言えば、ファンアートであっても、また、オリジナルが何なのかをわかるようにしていても、色を変えたり、アレンジを加えて公開したらアウト。同一性保持権の侵害。
 米国では、パロディが法で認められているので、その要件を満たしていれば合法ですが、肌の色を変えて、いくらかアレンジを加えただけでパロディと認められる余地はなさそうです。これがパロディとして認められるのなら、ありとあらゆる盗用はパロディで肯定されてしまいます。
米国では、パロディが法で認められているので、その要件を満たしていれば合法ですが、肌の色を変えて、いくらかアレンジを加えただけでパロディと認められる余地はなさそうです。これがパロディとして認められるのなら、ありとあらゆる盗用はパロディで肯定されてしまいます。
日本の同人誌やインターネットのファンアートは、権利者である漫画家や出版社が文句を言わないことが暗黙の了解になっているのですが、文句を言われたらそれまで。そういう猶予で成立しているだけであることを認識しておくことが必要ですし、その認識がある限り、肌の色をどうしたっていい。
だから私は「いいんでないかい?」と思ったのですが、Lynn6Thorexは肌の色を黒くしただけ、あるいは顔立ちを黒人風にしただけで、金をとっています。出典も明示してないと思われます。
「私は差別されてきた黒人なので、法を無視しても許される」として、色を黒くしただけで金を得ようとしているようです。同人誌も金を得ていますが、あれらは二次創作であり、場合によってはオリジナルを超えるものもあります。知らんけど。オリジナルの色を変えて同人誌として販売したら、さすがに暗黙の了解に反すると批判されましょうし、権利者も黙っていないかもしれない。
ファンアートの場合は、着色するだけのものもあるでしょうが、それは営利目的ではなく、作品への愛情への表れである点で容認されているのでしょうし、この場合もオリジナルを明示するなどのルールが必要がありましょう。さもないと、オリジナルであると誤解する人が出てきてしまいます。
その上、営利目的となると話は別です。英語圏での議論を見ると、ファンアートを販売する行為までを肯定する人たちもいますけど、そうなると、どんな盗用もファンアートとして肯定され、販売してもいいてことになりかねない。「どこまでがセーフで、どこからがアウトなのか」の線引きが必要であって、私は「営利か否か」が妥当な線引きだろうと思います。。
そんなこともわからなくしてしまうのが、「私は虐げられてきた黒人であり、奪われたものを奪い返しているだけ」という正当化です。作者の龍幸伸がこの人物を虐げ、何かを奪ったのであればまだしも理解ができますが、属性によって、法を超えて利益を得たり、権利を侵害されていいと思っているわけです。肌の色ですべてを決定すべきだと。「差別反対」の立場はこういう発想こそを否定するはずでは?
✴︎@Lynn6Thorexによる問題の投稿
エスカレートする「被差別者」の要求
![]() これを肯定したひとりが「ダンダダン」の英語版吹き替え版で、主人公の1人であるオカルンを担当したA.J.ベックレスという黒人声優です。自分が起用された作品の権利を侵害する行為を肯定ってどういう神経してんだか。何がポリコレだ、クソが(by 星子/ダンダダン)。
これを肯定したひとりが「ダンダダン」の英語版吹き替え版で、主人公の1人であるオカルンを担当したA.J.ベックレスという黒人声優です。自分が起用された作品の権利を侵害する行為を肯定ってどういう神経してんだか。何がポリコレだ、クソが(by 星子/ダンダダン)。
この発想に至るまでの経緯をざっくり説明しておきます。
そもそも英語圏でのドラマ、映画、コミック、アニメーションなどの創作物では、黒人が登場することは少ないという、おもに黒人たちの不満があります。人口比で考えると実際そうなのでしょう。これに対して、「黒人をもっと起用しろ」との主張が高まります。
そこで、端役に黒人を入れることで、「黒人を出している」という体裁を整えます。ドラッグの売人やかっぱらいに黒人を起用するとステロタイプだと批判されますので、主人公を中心とした5人で進行する物語に、ただそこにいるだけの黒人を登場させて6人にすることで、批判をクリア。
しかし、これに対しても、「おざなりの配役で誤魔化すな」という批判がなされます。つまり黒人を主人公にしないと納得しないのです。
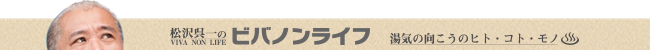
(残り 1272文字/全文: 3096文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。

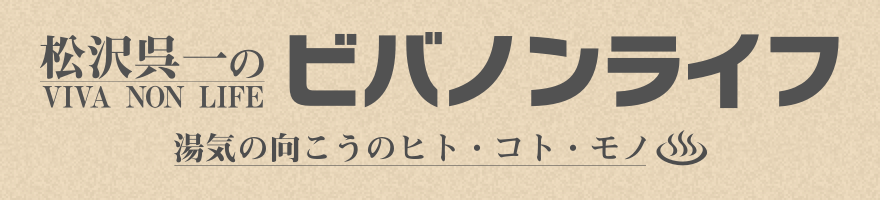







外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ