平塚らいてうは見抜いていた宗教的偽善者・神近市子—伊藤野枝と神近市子[7]-[ビバノン循環湯 465] (松沢呉一) -4,946文字-
「神近市子が殺そうとしたのは伊藤野枝だった—伊藤野枝と神近市子[6]」の続きです。
以前から「殺す」と口走っていた神近市子
![]() 「人を刺すほどのもんか?」といった程度の金額であっても、神近市子にとっては自分の優位性を証明する経済力も否定されたのですから、もはや何も残っていない。あとは憎き伊藤野枝を殺すしかないと思い詰めながらも実行できず、大杉栄を殺すしかなくなったのは前回見た通り。
「人を刺すほどのもんか?」といった程度の金額であっても、神近市子にとっては自分の優位性を証明する経済力も否定されたのですから、もはや何も残っていない。あとは憎き伊藤野枝を殺すしかないと思い詰めながらも実行できず、大杉栄を殺すしかなくなったのは前回見た通り。
「神近市子の内面を想像すれば」ということであって、ほとんどの人はこんなことで人を殺そうとはしません。人を殺そうとする閾値が神近市子はあまりに低い。異常と言っていい。
セックスがからむと異常になる人はよくいますが、その特異な性格や行動はそれ以前から見られたものでした。
神近市子の特異性は大杉栄著『自叙伝』でも十分わかります。
其晩は僕は麻布の彼女の家に泊った。そして翌日、保子のゐる逗子の家に帰った。すると多分其の翌日の朝だ、僕は彼女から本当に三行半と言ってもいい短かい絶縁状を受取った。それは「若し本当に私を思ってゐてくれるのなら、今後もうお互いに顔を合せないようにしてくれ。では、永遠にさよなら」と言ふやうな意味の、あまりに突然のものだった。僕は直ぐ東京へ出た。そして彼女を其の家に訪ふた。が、彼女は僕の顔を見るや、泣いてただ「帰れ、帰れ」と叫ぶのみで、話しのしようもなかった。そして僕は何にかを放りつけられて、其の家を逐い出された。
僕は直ぐ宮島の家へ行った。宮島の細君は彼女にとっての殆ど唯一の同性の友達だった。
「ゆうべはひどい目に合ったよ。神近君が酔っぱらって気違ひのようにあばれ出してね。そして君のことを『だました! だました!』と云って罵るんだ。漸くそれを落ちつけさして、家まで連れて行って、寝かしつけて来たがね。実際弱っちゃったよ。」
宮島は、僕が彼女の話しをすると、本当に弱ったやうな顔をして話した。
そこへ、暫くして、彼女がやって来た。顔色も態度も、さっきとはまるで別人のやうに、落ちついてゐた。
「私、あなたを殺す事に決心しましたから。」
彼女は僕の前に立って勝利者のやうな態度で云った。
「うん、それもよかろう。が、殺すんなら、今までのお馴染甲斐に、せめては一息で死ぬやうに殺してくれ。」
僕は其の「殺す」と云ふ言葉を聞くと同時に、急に彼女に対する敵意の湧いて来るのを感じたのであったが、戯談半分にそれは受け流した。
「其の時になって卑怯なまねはしないやうにね。」
「ええ、ええ、一息にさへ殺していただければね。」
二人はそんな言葉を云ひかはしながら、しかしもう、お互いの顔には隠しきれない微笑みがもれてゐた。彼女は又もとの姉さんに帰ったのだが、僕と伊藤とはこの姉さんにあまりに甘えすぎたやうだ。あまりに無遠慮すぎたやうだ。それをあまりに利用しすぎたとまでは思はないが。そして其のたびに彼女はヒステリーを起しはじめた。
「ゆうべはひどい目に合ったよ」というセリフは宮島資夫によるものです。「君」は大杉栄。神近市子がこうなった原因は大杉栄ですが、他の人の前でも酒を飲んで暴れるような人だったのです。
これはすでに大杉栄との関係が始まってからのものですし、刺されたために、大杉栄が神近市子の異常さをことさらに出しているとも言えますが、もともとそういう人だったらしきことは別の人の書いていることからも裏づけられます。誰が見てもどこかおかしな人だったのです。
なお、宮島というのはプロレタリア小説家の宮島資夫。今は「宮嶋」となっているものが多いのですが、戦前の著書は「宮島」になっています、弟の俳優、宮島啓夫も「宮島」と「宮嶋」の二種があって、「嶋」は面倒なので筆名や芸名は「島」にしていて、本名は「宮嶋」なのかと思うのですが、大杉栄も神近市子も「宮島」としていますので、ここでもそれに合わせます。
※神近市子の写真はここから借りました。おそらく「日蔭茶屋事件」を起こした頃のもの。どういう人かわかっているためもあって怖いです。
平塚らいてうの知る神近市子
![]() 以下は平塚らいてう著『現代の男女へ』(大正六)掲載「私の知ってゐる神近市子さん」より。
以下は平塚らいてう著『現代の男女へ』(大正六)掲載「私の知ってゐる神近市子さん」より。
彼女の顔も美人といふのではありませんけれど矢張り人に強い印象を与へる顔で、全体として堅く、引締った男性的な感じを有って居ました。けれども彼女の眼—特に大きな、いくらか飛び出た感じのする眼は、決して知的な、落着いた、そして内面的な深さをもったものではなく、寧ろ彼女がいかにパッショネートな婦人であるかを示したもので、絶えず涙ぐんでゐるやうな一種異様な刺激的な光は、何となく不安なやうな、恐ろしいやうな危険性を潜めて居ました。私は彼女のこの眼に出逢った瞬間何故といふ理由なしに、彼女は既に性の苦悶を経験した婦人だといふことを直覚したことも忘れずに言って置きませう。(略)後に私は或友達との会話の中で、彼女のことに及んだとき私はあの人の眼を見ると何だか怖い感じがする。あの眼は男—殊に女をよく知ってゐる男に対して妙な刺激的なものぢゃないでせうかといふやうなことを言ったのに対して、その友も同感だったことを今思ひ起して不思議な気がします。
この文章は「日蔭茶屋事件」のあとに書かれたものです。
 まず確認しておきますが、平塚らいてうは神近市子に同情をしていて、対して大杉栄や伊藤野枝には批判的です。ここでは神近市子を貶める意図はなくて、ただ自分の印象を書いているだけです。
まず確認しておきますが、平塚らいてうは神近市子に同情をしていて、対して大杉栄や伊藤野枝には批判的です。ここでは神近市子を貶める意図はなくて、ただ自分の印象を書いているだけです。
あとになって「そういえば」と悪い部分をあえて探し出しているのでもなくて、人とそのことを話すくらいに平塚らいてうにとってはいい印象がなかったのだと思いますし、上の大杉栄の記述の中に、宮島資夫の妻が「殆ど唯一の同性の友達」とあったように、とくに同性には好かれない人だったのかもしれない。
簡単に言えば「美人ではないけれど、エロい目をしていた」ってことです。これは初対面での印象ですが、その後も会っていて、なおその印象は変わらず、目だけでなく、素振りなり話し方にもそれが滲み出ていたのでしょう。
ここで言う「女をよく知ってゐる男」は当然大杉栄が含まれているわけで、「大杉栄もあの目にやられたのだ」と平塚らいてうは示唆しています。

(残り 2544文字/全文: 5188文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。







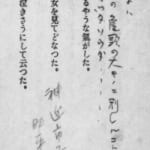
外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ