女の作家が男の名前で作品を発表した歴史を修正する試みとその批判—男の名前・女の名前[付録編5]-(松沢呉一)
「キラキラネームはただの雑誌の影響との説—男の名前・女の名前[付録編4]」の続きです。
彼女たちの栄誉を取り戻そうとして意思を踏みにじった出版社の例
![]() 名前に関する話題で見逃せない記事を見つけました。
名前に関する話題で見逃せない記事を見つけました。
2020年9月11日付「BBC」
このBBCの記事が的確かつ詳細にまとめていますが、かつて女の作家は、男であると思わせるペンネームで作品を出すことがよくありました。その作品の栄誉は男のものであるとされてきたことに対して、英国のベイリーズ(Baileys)という出版社が、女の作家が書いたものであることを明らかにするために、本名あるいは他で使っていた女のペンネームを冠して再発行する「Reclaim Her Name campaign」をスタートさせて、25冊の本を無料の電子書籍として発行しました。
これに対してすぐさま多数の批判が出ます。検索するとわかりますが、このプロジェクトを礼讃している人たちもいます。多くは出版社の主張をなぞっているだけ。
一方で、批判は研究者や批評家たち、つまりはこれらの作品や作家に精通している人々からなされている傾向があります。
これらの批判の論点は多様であり、表紙に使用されたイメージが他の作家のものだったなどのミスが発生したことは謝罪とともに差し替えればいいレベルの話として(事実そうしたようです)、たとえば男の名で書かれた小説の実際の著者は女の作家であるとの事実がなお確定していないものが含まれていることが研究者から指摘されており、これはケアレスミスでは済まないでしょう。本当の著者が男であれ女であれ、その栄誉を強奪したかもしれないのですから、このシリーズの意図を根底から覆してしまいます。
たしかにこの出版が意図するような主張に該当するような例はありつつも、大きくくくると「女の作家が男のペンネームにした事情はさまざまあって、その事情が見えなくなる出版である」ということです。
版元としては「本当は女の名前で出したいが、女の名前では評価されないので、やむなく男の名前にした」「女の名前では出版できず、版元から男の名前を強いられた」という物語で、すべてをまとめようとしたわけですが、そんな簡単ではないのだというのが最大の批判内容。
時に名前が作品を産む
![]() BBCの記事でもそれ以外でも、具体例が多数出ていますが、顕著なのはクィアな作家です。女というアイデンティティではない存在を求めて中性的なペンネームや男性的なペンネームをつけていて、「本当は本名で書きたかった」という版元の決めつけと正反対である可能性があります。
BBCの記事でもそれ以外でも、具体例が多数出ていますが、顕著なのはクィアな作家です。女というアイデンティティではない存在を求めて中性的なペンネームや男性的なペンネームをつけていて、「本当は本名で書きたかった」という版元の決めつけと正反対である可能性があります。
たとえば改名したトランスジェンダーの死後、改名後の名前ではなく、わざわざ本人が嫌ったデッドネームで本を出し直すことがどれだけ不当であるかを考えればわかりましょう。
トランスジェンダーだけでなく、ペンネームは表現する際の別人格の設定だったりします。レディ・ガガも、友だちが本名で呼ぶことを禁じていたことがあるらしいですよ。別人格に対して「足を引っ張らないでくれ」ってことです。友人・知人がこれまで呼んでいた名前で呼ぶのは自然ですけど、人によってはことさらに人前でそれを誇示することもありますしね。
男が女のペンネームで書くこともあるのに、女というだけで「本当は本名で書きたかった」と決めつけることこそが間違ったジェンダー・バイアスです。
そもそも人はなぜペンネームを使うのか、有名作家になってもなお別名で書くことがある(その例もBBCの記事は取り上げています)のはなぜなのかを考えれば、第三者がその意図を一律に決めつけることの傲慢さがわかろうかと思います。

(残り 1744文字/全文: 3347文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。


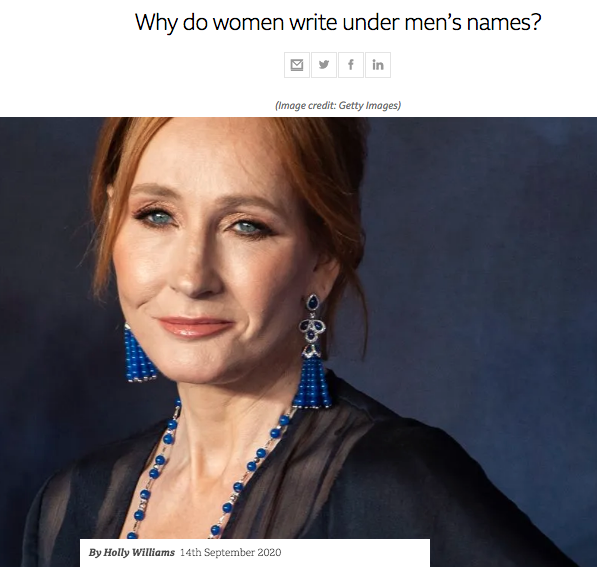




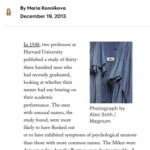


外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ