歳をとってもモテたい。でも、人による—男は年齢ではない。でも、人による 上-[ビバノン循環湯 279] (松沢呉一) -3,349文字-
[「ちょいワルジジ」になるには美術館へ行き、牛肉の部位知れ]って記事が炎上しているそうですね。「ケッ」と思うのはわかるけれど、真剣に叩くようなもんじゃねえだろ。エロジジイの子どもじみたファンタジーにいちいちつきあってんじゃねえよ。暇か。
結果、雑誌のプロモーションとしては大成功でござる。
こんなもんに青筋立てている暇があるんだったら、職業上の立場を利用し、なおかつ薬物まで使った可能性があって、逮捕状まで出ていたのに、官邸に泣きついて逮捕を免れたと見られる山口敬之ってジャーナリストとそれに加担した警察の幹部と官邸に怒った方がいいと思うぞ。
そりゃ、薄汚いジジイに迫られたら不快だろうけどさ、トム・クルーズを老けさせたようなジイさんが美術館で声をかけてきたら、十人に一人くらいはお茶くらいは飲んで、そのうちの十人に一人くらいはラブホでもどこでも行くべ。
つまりは人によりけりであって、あの記事は写真を出したのが失敗かもね。「こいつかよ」って感じ。
若いバンドマンが「女とセックスするためにバンドを始めました。セックスした女でライブハウスを満員にしたい」とか言ったところで、「アホなヤツ」で済まされるでしょう。「夢があってよろしい。でも、どうせだったら武道館と言え。若いんだから夢は大きく」と私は思いそう。
「美術館は静かに一人で美術作品を鑑賞するところだ。美術に対する冒涜だ」と言う人たちは若い世代向けにデートコースとして美術館を推奨する雑誌記事にも目くじら立てるんですかね。最後はラブホでハメるための前戯に美術館を利用してんだぜ。私なんて若い頃、美術館でデートして、誰もいないのをいいことに、パンティの中に手を入れたことだってあるんだぜ。完全に前戯。プッシー・ライオットの母体VOINAなんて美術館で集団セックスしたんだぜ。前戯じゃなくて、本編。
結局のところ、「セックスは若い世代の特権であって、ジジイは家で静かに盆栽でもやっていればいい」という社会的視線が、あの記事を炎上させただけじゃないんですかね。老人を大切に。老人の性欲も大切に。あんくらい許したれよ。どうせもうじき死ぬんだから。
実際、60代でも70代でも、なおチンコが現役の人はゴロゴロいます。ナンパしたら叩かれる。迷惑をかけないように出会い系に行ったら、読売新聞に叩かれる。どうしろと。
 それも人によりけりで、もはや私は全然その気がない。性欲がないわけではないけど、それに関わる手続きやらなんやらが面倒。
それも人によりけりで、もはや私は全然その気がない。性欲がないわけではないけど、それに関わる手続きやらなんやらが面倒。
私ももう汚いジジイになってきているので、写真も自分では出さないようにしていて(「ビバノン」のタイトルには出してますが、これは編集部の要請)、この先は目立たないようにひっそり生きて、ひっそり死んでいけばいいと思っています。
枯れていくことも受け入れていて、いまさらモテたいなんて欲望もなく、若くてかわいい男の子のケツを見てれば幸せですけど(男の子に胸をときめかせるようになったのも老化現象だと思ってます)、40代までは衰えていく自分に対する焦りがありました。チン毛に白髪が混じっていることに気づいた時のショックたるや。
今回循環するのはその時期に書いたものです。これも発表する機会がなくて、メルマガ読者用のevernoteが初公開ですが、書いたのは十年以上前。
半分は冗談ですけど、半分は本気。その頃は、歳を食っても遊んでいる50代、60代は希望でした。「まだまだオレは大丈夫だ」と。昔の流行作家たちは、若い女と遊んでいることを自慢げに書いていたわけですけど、あれも希望を与えていたのだと思います。
その意味では、私も「いまなお若い小娘と毎夜セックスしているぜ」とハッタリかました方が下の世代に希望を与えましょうが、「歳をとったら自然と枯れて、どうでもよくなる」という現実を見せておくことも必要でしょう。それはそれで楽ってことですから、私はそっちの役割を担当します。
前文が長くなったので二回に分けます。
※Florine Stettheimer「The Cathedrals of Art」
「まったくない」点で共通する某局アナと私
![]() あるテレビ局のアナウンサーとダベッているうちにわかったのだが、彼と私は対照的。彼は家庭第一なのである。
あるテレビ局のアナウンサーとダベッているうちにわかったのだが、彼と私は対照的。彼は家庭第一なのである。
「子どもができるまでは妻のことが大好きで、子どもができてからは子どもが大好き。愛情が子どもに向かったので、妻がちょっとすねてますけど、子どもの顔を見に家に帰るのが楽しくてしょうがない」
「もちろん今も妻のことは好きで、浮気なんてする気はまったくない。松沢さんは家庭を持つ気はないんですか」
「まったくない。まったくない同士で仲良くしようぜ」
方向が見事に違うわけだが。
私は持論を開陳した。
「家は一人になれるから好きなんであって、家族がいたら一人になれないじゃないか。家に他人がいたら帰りたくなくなるよね。人生、何が起きるかわからないけど、一生結婚はしないと思うなあ」
「でも、子どもはホントにかわいくて、家に早く帰りたいですよ」
「かわいいかもしれないけど、三時間も一緒にいれば飽きるだろ。月に一回遊んでやるだけでいいなら子どもがいてもいいけど、毎日いられたんじゃたまったもんじゃない」
「いやー、そこまで徹底している人も珍しいですよね」
私としては自分が楽でいられる方に進んできたらこうなっただけのことで、自分が珍しい存在であること自体信じられない。みんな、自分がどうすれば楽になるのかを突き詰めてないのではなかろうか。
私の不安
![]() 「不安になることってないんですか」と彼は真剣な表情で聞いてきた。たぶん彼は性格上、私のような状態に置かれたら不安で不安でしょうがなくなるのだろう。
「不安になることってないんですか」と彼は真剣な表情で聞いてきた。たぶん彼は性格上、私のような状態に置かれたら不安で不安でしょうがなくなるのだろう。
「実はオレにも不安はある」
私は正直に答えた。
 一人暮らしが長いと、精神状態が不安定になりやすいような気がする。気晴らしや仕事の目的みたいなものを家族に求められないため、煮詰まるときはとことん煮詰まり、「オレはなんでこんなことをやっているんだろう」との迷いが生じやすい。
一人暮らしが長いと、精神状態が不安定になりやすいような気がする。気晴らしや仕事の目的みたいなものを家族に求められないため、煮詰まるときはとことん煮詰まり、「オレはなんでこんなことをやっているんだろう」との迷いが生じやすい。
必ずしもそうじゃない夫婦もいるだろうが、妻がいれば悩みの相談もでき、協力しあうことで問題の解決がしやすい。
それ以前に家族を支えていかなければならないと、煮詰まったり、迷ったりしている暇はなく、がむしゃらに働くしかない。すべては「家族のため」という目的に収斂しやすいため、「何故」というところで立ち止まることが少ないのだ。
といった点で、一人暮らしはデメリットもあって、事実、私はこのところ、精神状態がずっと低迷している。

(残り 494文字/全文: 3416文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。


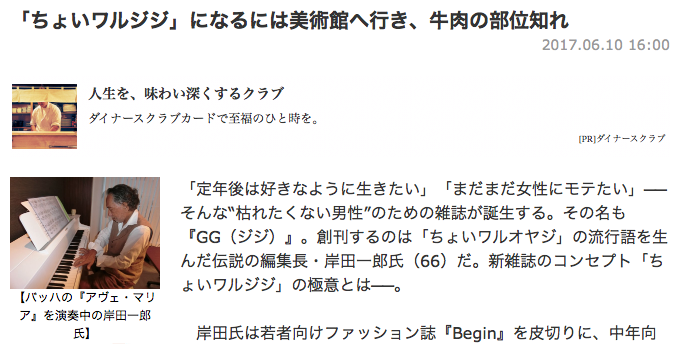






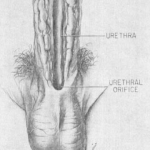
外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ