薬漬けの明るい未来—星新一の父・星一が書いたSF小説『三十年後』[下]-(松沢呉一)
「星製薬社長にして国会議員—星新一の父・星一が書いたSF小説『三十年後』[上]」の続きです。
星新一のルーツは星一著『三十年後』か
![]() 京谷大助著『星一とヘンリー・フォード』に続けて、星一著『三十年後』(大正7年)を読みました。明るい未来を描いたSFです。このセンスが息子に伝わったのでありましょうか。
京谷大助著『星一とヘンリー・フォード』に続けて、星一著『三十年後』(大正7年)を読みました。明るい未来を描いたSFです。このセンスが息子に伝わったのでありましょうか。
序文に「江見水蔭君を煩はせしこと極めて多し。茲に此事を書して深く同君の労を謝す」としか書いていないですが、この本は口述筆記で、実際に書いたのは作家の江見水蔭(えみ すいいん)らしい。
大正7年、政治家の嶋浦太郎は親族が皆他界したことを機に60歳で隠遁することを決意して、無人島暮らしを始めます。無人島でどうやって食べていたのか書かれていないですが、たぶん野良仕事をしたり、釣りでもしていたのでしょう。
太郎はその生活が気に入っていたのですが、大正37年、島が水没することになったために、90歳で戻ってきます。30年間、太郎は一切人に会わず、情報にも触れていなかったため、日本も世界も大きく変貌していて、太郎は戸惑います。
 大正37年の日本では、星製薬社長の星一が救世主となって(笑)、病気も狂人も犯罪者も危険思想もすべて薬によって改善されていました。星製薬が薬を輸出することで莫大な収益があるので、日本は豊かになり、貧困は消えてました。貧しい国には薬を無償で提供し、心身ともに人類は健全化し、警察や軍隊も不要となって、世界は平和になっていました。
大正37年の日本では、星製薬社長の星一が救世主となって(笑)、病気も狂人も犯罪者も危険思想もすべて薬によって改善されていました。星製薬が薬を輸出することで莫大な収益があるので、日本は豊かになり、貧困は消えてました。貧しい国には薬を無償で提供し、心身ともに人類は健全化し、警察や軍隊も不要となって、世界は平和になっていました。
古来、宗教や思想で社会を変革して理想を求めたのに対して、星一は薬で理想を実現したのでした。
病気や異常を治すだけでなく、能力を高める薬も開発されていたため、プロの小説家や音楽家、スポーツ選手はいなくなってました。誰もが薬を飲めば優れた小説を書け、歌がうまくなり、運動能力が高くなるからです。
寿命は150歳まで伸びてましたが、回春薬で老化も抑制されているので、老人らしい老人はおらず、白髪も薬でなくなります。すっかり老人となった太郎は珍しがられて講演会に引っ張りだこですが、これでは見世物だと怒ると、巡視官がやってきて薬を飲まされます。
警察は存在しないのですが、脳に異常がないか見回るための巡視官がいて、サーベルのような機械で脳の異常を発見し、薬を飲ませて万事解決。抵抗すると強制入院です。太郎は脳の感情部分に異常があったのです。
太郎は穏やかになり、また、若返りの薬を飲んで見た目も若くなり、その薬が効き過ぎてか、小娘に恋をしてしまいます。
というところからラブロマンスが始まるという内容。ここまでは前提であって、これから始まる本編は国会図書館でお読み下さい。
未来予測が当たったのは極わずか
![]() タイトルからしても、エドワード・ベラミー著『百年後の社会』を踏まえていることは間違いなく、展開も似たところがありますけど、最後のオチは星一の方がずっと厚かましい。自分で書いたわけではないがゆえにできたのでしょうけど、それにしてものラスト。
タイトルからしても、エドワード・ベラミー著『百年後の社会』を踏まえていることは間違いなく、展開も似たところがありますけど、最後のオチは星一の方がずっと厚かましい。自分で書いたわけではないがゆえにできたのでしょうけど、それにしてものラスト。
 「夢枕」と言われる録音機はすでに実現したと言っていいでしょう。この時代にも蓄音機はあったので、そこから自分で録音できる機械まではそう離れてはいない。
「夢枕」と言われる録音機はすでに実現したと言っていいでしょう。この時代にも蓄音機はあったので、そこから自分で録音できる機械まではそう離れてはいない。
また、自動歩行器というのが出てきます。セグウェイみたいなものです。案外実用化までには時間がかかりましたが、これも実現。
無線機で連絡を取り合うことになっていて、これは携帯電話。この頃、無線機はすでにあっても、人の声をそのまま送れるようにはなっていなかったのではなかろうか。
未来の先取りとして実現したことはそのくらい。車はほとんどなくなっていて、その代わりに小型飛行機(本書の巻頭挿絵もこれ)が多用されているといった話はまるで当たらず。
肝心の薬については想定していたことのうち実現したのは100分の1くらいか。
※「官報」1919年12月12日発行号より。こんな商品も出していました。養命酒みたいなものでしょうか。

(残り 1819文字/全文: 3480文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。




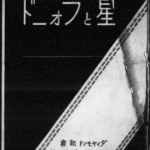


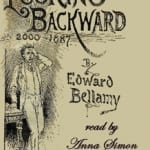
外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ