老嬢(オールドミス)になることの恐怖—女言葉の一世紀 74-(松沢呉一) -3,338文字-
「吉屋信子になれない女たちの仕事—女言葉の一世紀 73」の続きです。
独身女はこんなに悲惨
![]()
看護婦と並んで、独身でも続けられ、高給ではないながら安定した収入が得られ、なおかつ需要が多いのは教員です。小学校であれば全国津々浦々に勤務できる学校があり、師範学校を出る人の数がまだ少なかったのですから、女でも師範学校を出ていれば確実に教員になれ、実際に、独身を貫いた人たちもいたようです。
前出の川崎利太著『結婚読本』(昭和十一年)には「悲痛なる老嬢の叫び」という章があります。著者が五十代の独身女性教員から聞いた話とのことですが、ちょっとおかしなところがあります。
お茶の水のことだと思いますが(前に説明したように、「お茶の水師範学校」「お茶の水女学校」は当時の正式名称ではありません)、彼女は女子高等師範学校を優秀な成績で卒業し、某県の女子師範学校の数学の教員になったとあります。

しかし、女子師範学校を出ても、師範学校の教員にはなれなかったんじゃなかろうか。無試験でなれるのは高等小学校(旧制中学)までで、試験を通れば高等女学校の教員にまではなれるはず。あるいは試験を受ければ師範学校の教員にもなれたのかな。ここははっきりわからないので、飛ばすとして。
彼女は若い時分は自信満々で、周りからもチヤホヤされ、自分に見合うのは大学を卒業したエリートであって、同僚から言い寄られても相手にせず、縁談も断ります。
しかし、三十代になると両親が亡くなり、学校では「いつまでやっているのか」と陰口を言われるようになります。教員でも結婚をすると辞めるのが多かった模様です。
かつては生徒から人気があったのに、「ヒス」と称されるようになり、気づいた時には婚期を失し、持ち込まれる縁談は老人の再婚相手で、いまさらそれを受け入れることもできない。
やがて閉経を迎え、子どもを残せないことに「人類全体への叛逆を敢えてしたやうに思った」とあって、ここでやっぱり創作だなと。前回確認したように、これはこの本の著者が言っていることそのままです。そんなこと考えないでしょ、普通。展開もすべてステロタイプです。
この元になる話が仮にあったとしても、著者が大幅に脚色していることは間違いない。今もこういうことをやる人はいるでしょうけど、昔の人たちはこういう創作、脚色をやりすぎかと。
※東京女子高等師範学校編『東京女子高等師範学校沿革略志』(大正四年)より明治二十五年完成の校舎。こちらは附属女学校ではなく、師範学校本体です。

(残り 2546文字/全文: 3618文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。




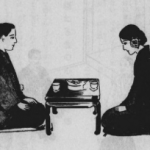



外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ