フェイクニュースを判定する困難と危険—ポグロムから学んだこと[2](松沢呉一)
「マーク・ザッカーバーグを支持する—ポグロムから学んだこと[1]」の続きです。
デマをどう抑制していくか
![]() 以前書いたように、デマ、誤報の類いを根絶まではできないとして、いくらかでもセーブする仕組みを作れないかと考えていた時期があります。「ビバノン」がうまくいったら、「タグマ!」をからめてそういう仕組みを作りたいと思っていたのですが、「ビバノン」の購読者は伸び悩んでとてもそこに行きつけない。
以前書いたように、デマ、誤報の類いを根絶まではできないとして、いくらかでもセーブする仕組みを作れないかと考えていた時期があります。「ビバノン」がうまくいったら、「タグマ!」をからめてそういう仕組みを作りたいと思っていたのですが、「ビバノン」の購読者は伸び悩んでとてもそこに行きつけない。
ここまでさんざん「リテラシーの向上を」と多くの人が繰り返してきましたが、まったく改善されていない現実を見れば、いくら言っても無駄であることは明らかです。
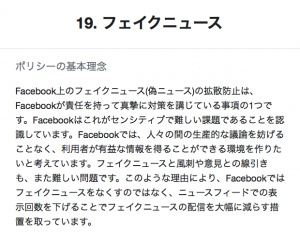 意図的にデマを流すのは問題外として、調べること、考えることを放棄して、感情に任せて見境なく書き込む人たちがいる限りは改善されない。なおかつ、普段は慎重な人でも軽卒なことをやりやすい環境というのがあります。SNSはそういう環境。
意図的にデマを流すのは問題外として、調べること、考えることを放棄して、感情に任せて見境なく書き込む人たちがいる限りは改善されない。なおかつ、普段は慎重な人でも軽卒なことをやりやすい環境というのがあります。SNSはそういう環境。
うっかりは誰しもありますが、間違いを指摘しても無視してすっとぼける。プライドが邪魔して間違いをなかなか認めない。これがデマを拡散する。
こういうタイプはSNSをやめる以外に適切な対策はない。しかし、やめてくれないので、「運営は投稿やアカウントを削除しろ」ということにもなってきますが、私はそれをよしとしないので、他の方法を考えるしかない。
私がその時に構想していたことを具体的に言うと、その中身を検証するチームを作り、間違いだと判明した段階でその検証内容を公開するとともに、情報を出した元を特定して公表する。また、拡散している人たちに間違いだと直接知らしめるシステムです。
「ビバノン」だってそうですけど、校正がないと誤字脱字は避けられない。校閲がないと事実関係の間違いが起きてしまう。能力が高い校閲として知られる新潮社の校閲だって見逃すことはあります。校正レベルのことまでやってられないとして、事実関係の間違いだけは外部で調べて訂正していくってことです。
意図的に流していようと、うっかりであろうと結果は同じですから、その人物を特定することで周りに「この人は要注意です」と呼びかける。また、晒し者にすることで、本人の反省を促し、自ら撤回させる。自ら撤回はしない以上、晒すことで恥をかかせるしかないだろうと思います。
検閲や焚書につながる発想
![]() もしこれが実現して、SNSの運営が「間違いだと判明した段階でこちらで削除するようにしましょうか」と言ってきても断ります。検証チームが「間違いだ」と判定したとしても、この判定もまた間違っていることがあり得ます。今ある情報では間違いだと判断できても、今ある情報が十分であるとは限らず、明日には覆るかもしれない。
もしこれが実現して、SNSの運営が「間違いだと判明した段階でこちらで削除するようにしましょうか」と言ってきても断ります。検証チームが「間違いだ」と判定したとしても、この判定もまた間違っていることがあり得ます。今ある情報では間違いだと判断できても、今ある情報が十分であるとは限らず、明日には覆るかもしれない。
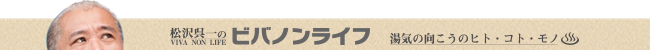
(残り 1802文字/全文: 2980文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。

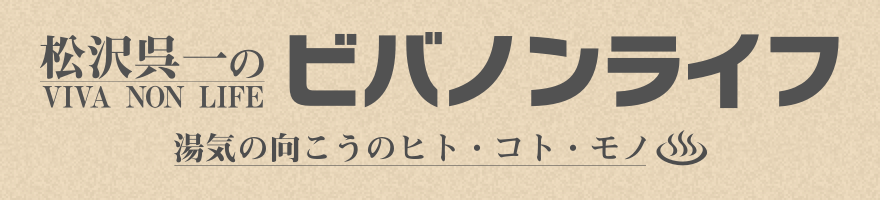






外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ