ラトビアの補足とエストニアとの比較—国外脱出したロシア人たちの苦渋[8]-(松沢呉一)
「ロシア人の亡命申請に苦慮するフィンランド—国外脱出したロシア人たちの苦渋[7]」の続きですが、内容は「公用語を話さない人々を甘やかしてきたラトビアの反省—国外脱出したロシア人たちの苦渋[5]」からつながってます。
ラトビアのエグネレ法務大臣のインタビュー
![]()
ここまで書いてきたことの補足ですが、ドイツのDWがラトビアのエグネレ(Inese Lībiņa-Egnere)法務大臣のインタビューを公開。グッドタイミング。
前半はロシア語排除についての弁明です。どうやらラトビアはロシア語放送を禁止したようです。これに対する批判があるのですが、「ビバノン」で書いてきたように、ロシア語話者があまりに多いラトビアでは、やむを得ない措置です。
あくまでロシアから発せられるプロバガンダ放送だけであって、禁止しようにも、国境近くではラジオはもちろんテレビの電波も拾えますし、インターネットも同様ですけど、CATVなどによる放送は禁止ということだろうと思われます。
TVレインのような反政府ロシア語放送は残るのではないかと思いますが、TVレインはラトビアのルールを守れなかったことの制裁として潰されたとしてもやむを得ない。プロパガンダ放送とは別の根拠です。
ここまで見てきたように、ラトビアはロシア語しか話せない人々をなくして、国民は全員公用語であるラトビア語を理解できるようにしようとしています。
これまでもロシア語放送では字幕を必ずつけるのがルール。ロシア語がわからない人もチェックができ、字幕によって少しはロシア語話者がラトビア語に親しむようにという工夫です。それは親プーチン派放送か反プーチン派放送かを問わない。TVレインは定められた間にそのルールを実施できなかったわけですし、そうなったのはロシア人の思い上がりだとしか私にも思えませんでした。
エストニアとラトビアとの比較
![]()
エグネレ法務大臣は、新型コロナの情報に対しても一定の規制が肯定されたことを例に出していますが、そっちは各SNSや映像のサイトの自主規制にすぎず、国家がそれをやった例は多くはないのではなかろうか。中国発祥説を消して回った中国はいざ知らず。
したがって、新型コロナによるメディア規制はあんまりいい例ではないかと思われますが。ロシア国籍の人々が国内に多数いて、ラトビア人の4分の1がロシア語話者である特殊性を考慮に入れず語ることは難しいでしょう。
現状ではやむを得ないとは言え、本来はロシア語話者を甘やかさないことで解消すべき問題だっただろうと思います。そちらの対策も進んでいます。公立学校からのロシア語排除は来年からだと思っていたのですが、来年度、つまり今年の9月から実施のようです。訂正しておきます。
これらの急速なロシア語排除政策には国内外からの批判もあるのですが、同じくバルト三国のエストニアでは、とっくにロシア系住民に市民権を与える際に、エストニア語の試験に合格することを条件にしてきました。
歴史的経緯はラトビアと同様で、第二次世界大戦中にソ連に占領され、一時ナチスドイツに占領され、1944年から1991年まではソ連に占領されていて、この間にロシア人が多く移住してきました。
ソ連崩壊によって、エストニアにおいてはソ連の国籍は失効したようで、改めてロシア国籍を取得した人々がエストニア居住者全体の8パーセント程度を占めています。また、ロシア国籍もエストニア国籍もとらないまま、無国籍者になった者たちもいます。市民権をとろうとしなかった人々と、ラトビア語ができないために基準を満たせなかった人々です。
今現在ロシア系は20万人以上いて、総人口120万人のエストニアに占めるロシア系の割合は22パーセントに及びます(ロシア国籍と無国籍を含めての総居住者に対する率)。ラトビアより少し少ないですが、2割を超える。そのほとんどは首都タリンとロシアとの国境近くのエリアに住んでいます。
ロシア・コミュニティを形成して、その中で完結する生活をしている人たちが多いのはラトビアと同じ。その最大拠点が国境沿いのナルヴァ(Narva)です。「今年の戦勝記念日—博物館とアーティストとロシア兵による抵抗」に出てきた場所です。
エストニアで三番目に人口の多いナルヴァでは、住民の95パーセントがロシア系。
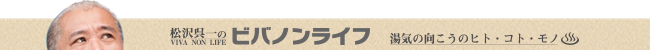
(残り 1394文字/全文: 3318文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。

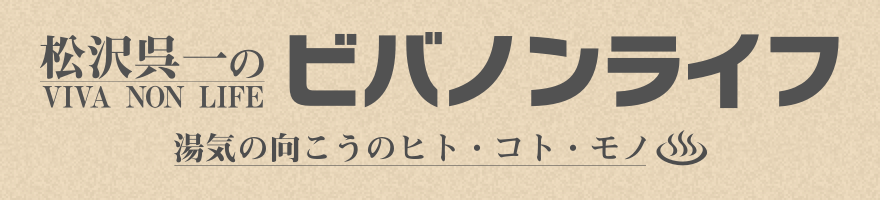



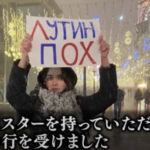


外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ