エルヴィス・コステロ『(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love, and Understanding 』 あの頃みんなパンクという新しい風に吹かれて何かしなあかんという気持ちにさせられていたのです
日本だと社会が不安になると、ジョン・レノンの「イマジン」がもてはやされますが、海外では10年以上前から現在の閉塞感ある空気を代表される曲としてもてはやされるのはニック・ロウの「(ワッツ・ソー・ファニー)ピース・ラブ・アンド・アンダースタンディング」です。
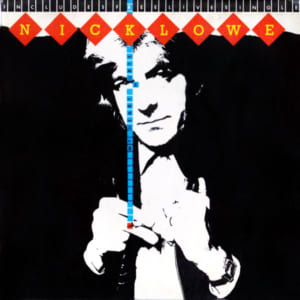 その理由は、ソフィア・コッポラの『ロスト・イン・トランスレーション』で、主人公を演じたビル・マーレーがこの曲を歌ったからだと思います。
その理由は、ソフィア・コッポラの『ロスト・イン・トランスレーション』で、主人公を演じたビル・マーレーがこの曲を歌ったからだと思います。
なぜこんなレアな曲を彼がカラオケで歌ったのでしょう。ソフィアのイメージは、彼女の友達の故編集者林文浩と日本でカラオケに行った時に彼がアナーキー・イン・ザ・UKを歌ったことから来てるのです。
カラオケというカウンター・カルチャーから何百光年も離れた世界で「アナーキー・イン・ザ・UK」をがなる状況は、今の僕たちが置かれているジレンマに見えたのだと思います。
ビル・マーレーに「アナーキー・イン・ザ・UK」を歌わせてもよかったんですが、ボディガードの大ヒット『サントラ』に入っていたとはいえみんなから忘れ去られようとしていた曲を使ったのはセンスがいいとしか思えない。ヒッピーの挫折感を歌ったこの曲でニック・ロウはサントラの印税で3億入ったそうです。ニック・ロウ不思議な人です。
ソフィア・コッポラの時代の空気を感じるセンス、お父さん譲りでしょうかね。お父さんは『地獄の黙示録』で、これまた忘れ去られようとしていたドアーズの「ジ・エンド」を使い、パンクは始まっていたんですけど、これから世代闘争が始まるであろう時代の流れを古ぼけたヒッピー・ソングで再現しました。
でも両者とも何のことを歌っているの分からないですよね。だから僕が解説したいなと思います。「ジ・エンド」の方はまた今度にさせていただきますが。
正確に書くと今の空気を代表しているのはエルヴィス・コステロのヴァージョンの方です。
歌詞は一切変えていないのですが、この2曲実はとってもメッセージが違うのです。ニック・ロウのヴァージョンは、要約すると俺たち革命を失敗して、こんな世の中になってしまったけど、でも愛と平和と調和(総合理解って訳した方がいいですかね、でもヒッピーの用語はピース、ラブ、ハーモニーだったのですよ)を語ることが何でおかしいの?って言う歌です。
1974年のヒッピーの挫折曲を、コステロはパンクの勢いを感じて、いつまでたっても俺は愛と平和と調和って言い続けてやるぜと歌っているのです。
ニック・ロウもコステロもパンク以前の世代のアーティストです。でもコステロはパンクの登場に合わせてキレキレで演奏するようになるのです。YouTubeに1978年とかのライブを見ると本当にキレキレでライブをやっていて、かっこいいです。僕もちょうどこの時のライブを観てるんですが、それはそれはカッコよかった。この時はみんなキレキレでした。XTCの初来日も観てるんですけど、キレキレでした。これはちょっと嘘です。この時はキーボードのバリー・アンドリュースが抜けて、ベースのコリン・モールディングが「労働者のナイジェルは一生懸命頑張っている」みたいな歌を歌い出していました。
この時期のキレキレのライブをしてたのはストラングラーズでしょうね。初ライブの録音テープを聴いたのですが、日本のお客さん、歌詞も分かんないのに、とんかくガナっているのです。多分パンクという思想にみんなやられていて、なんかしないといけないという高揚感がそうさせていたんだろうなと思います。
同じ会場で見たポリスもそんな感じになっていました。ただ単に呼び屋さんと会場を貸した学生の自治会とが、契約の問題で揉めていただけなんですけど、コンサートは中断され、関係ないお客までステージに上がって、関係ないことまで色々喋っていました。時代の空気がそんな感じだったのです。
あの頃とにかくみんなパンクという新しい風に吹かれて何かしなあかんという気持ちにさせられていたのです。

(残り 1738文字/全文: 3374文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。


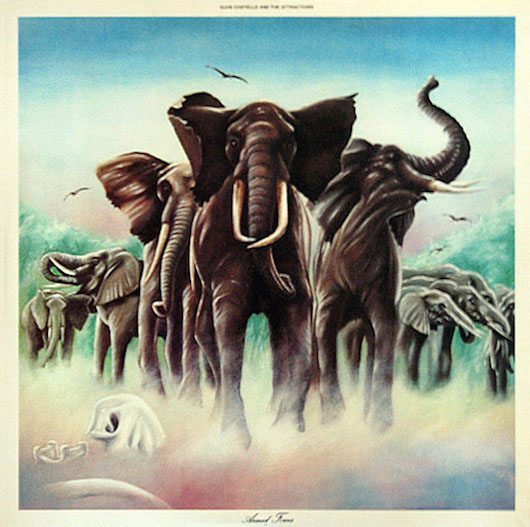


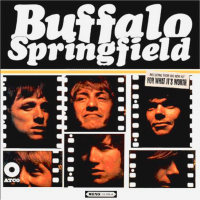

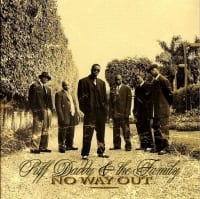
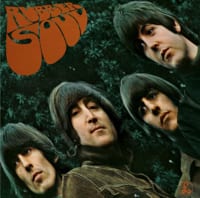
外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ